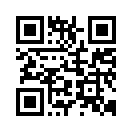2008年06月27日
Away from her

初老の女優が「ドクトル、ジバゴ」のジュリークリスティーだなんてわからなかった。でも、映画を見ているうちに、その美しさに引き込まれて行く。
マカデミー女優主演賞にノミネイトされ、ゴールデングローブ賞を初め、ニューヨーク不評家賞など、数々の賞を取っている。
カナダの雪景色の中で、カントリースキーをしている夫婦の通る跡が、平行して並んで刻まれているが、そこから、一つの線がそれて離れていく。
映画の冒頭のシーンは、寄り添って共に暮らして来たはずの夫から、妻の心が離れて行き、再びスキーの跡が平行に戻ることで、妻の心が戻ってくるという事を暗示している。
アルツハイマーになった妻は、施設に入居することを決心する。慣れるまでの間、1ヶ月は面会が赦されない。面会解禁の日の朝、夫は彼女に会いに行く。
そこには、車椅子の男性に寄り添う妻がいた。献身的にその男の世話をする妻にとって、夫は見知らぬ人になり、恋に夢中になっている。
夫は、自分が罰せられているのだと思い、彼女に会いに日参するが、彼女の恋を見守ってやらなければ、と思うようになる。
介護士から「夫は、まあ良い人生だった、と思うが、妻はそう思ってはいないのですよ。」と言われる。
夫は大学の文学教授で、若い頃は女学生に片っ端から、かりそめの恋をした。
18才の学生だった妻から、「結婚しませんか。結婚生活って楽しいのではありませんか。」と誘われ、彼女は、美しく魅力的だったから結婚した。
以来、夫の恋心は、治ることはなく、20年前に女子大生との問題が発覚してスキャンダルとなってから、大学を退職し、妻と二人でやり直す為に、妻の祖母の別荘だった家で暮らして来た。
「私を捨てる事だって出来たのに。あなたはそうはしなかった。あなたに迷惑をかけたくないのよ。」というのが入所理由だと妻は言う。夫の浮気を知りながら、口に出すことをしなかった妻が、アルツハイマーになって心の内を語り始めた。彼女には辛く、心の奥に深い痛みとなっていた、夫の裏切り。彼女はやさしく夫に寄り添いながら、夫を赦してはいなかった。
車いすの男性が、施設を出て行くと、ベッドから離れず、哀しみから立ち直れない様子で、二階の重傷患者の部屋に移すことになる。
夫は、退院した男性の家を訪ねる。その妻の話を聞けば、自分達夫婦の生活は恵まれて、幸せだったのだと気づかされる。家に帰ると、彼女からの誘いの留守番電話が。ダンスパーティーへの誘いだった。その夜、二人はベッドを共に。夫を病院に再び入れる為に、彼女は家を処分する。 夫は、妻の為に、恋人を病院に連れて行き、残された者同士、新しい人生を選ぼうとした。扉の前で、看護士と男性を待たせて、先に妻に挨拶してから、と中に入ると、妻は、夫がいつも読んでやっていた本を自発的に読んでいて、夫を認識出来るようになっていた。
「早く退院の手続きを取って。家に帰りたいわ。あなたは、私を捨てることだって出来たのに、あなたにはとても感謝しているの。」
妻が入所以来、初めて、夫に抱きついて、抱擁する。複雑な表情をする夫。
映画の中で、ジュリークリスティーが、赤の縞模様の派手なカーディガンを着ている。
夫は「あんな安物の服を彼女が着たことはなかった。どうしたのだ。誰のものなのか。」と看護士に聞く場面がある。それまでの、ジュリーの服装は、上品で、色は白かベージュの無地で、エレガントで知的、初老の女性の美しさを際だたせたものだった。
花束を持って面会に来る夫は、入所している女性患者から、「女垂らし、女を泣かせたんでしょうね。」と言われるように、ダンディーで紳士的な男性。
妻は、夫の為に、夫に気に入られようとして無理していたのではないだろうか。本来彼女は自由奔放な女性だったはず。18才で夫に結婚を自ら提案した女性だった。「結婚すれば楽しいんじゃない?」
「あなたは私を捨てる事も出来たのに。」という言葉の中に、年の離れた教授の夫の好みの女性にならなければという、抑圧関係が表れている。本来の彼女は、ナチュラルな女性だった。自然そのものだった。彼女が身をかまわなくなってゆくのは、本来の自分に戻っただけのこと。夫に気に入られるような服装をやめ、優しく真面目な、浮気をしたこともない、車椅子の男性に恋をする。世間の衣を脱ぎ捨てた彼女は、病を得て、自由になった。夫は、夫で、「自分たちの生活とはかけ離れた、過酷な暮らしの中で、現状を受け入れ、人生に折り合いをつけている人間がいる」ということを初めて知った。彼は、普通の、人生の楽しみを味わった事もない、インテリとはかけ離れた女性の、ストレートな求めに、初めて応じた。
別れを告げに行ったはずの夫に、妻は抱きつき、抱擁する。彼女に取って、おそらく
最初に出会い、燃え上がる恋をした男が、そこに存在していたからだろう。
2008年06月24日
誰がために鐘は鳴る
 1943年作品
1943年作品宝塚ソリオホールで映画会が時々催される。母の元に届いた映画会の案内書に「誰がために鐘は鳴る」のちらしがあり、母は、カレンダーに印をつけて行くのを楽しみにしていたらしい。
当日の朝、電話があり、起きるとすぐに、「今日は「誰がために鐘はなる」を見に行く 」と言っていますよ、とお嫁さんから。
最近、母に、映画に行こうと誘っても、「もう行く気がしなくなったわ。見てもすぐに忘れるから」と言うばかりなので、「ビデオがあるから、それを見てもらえば? ソリオホールの椅子が固くて、座っているとお尻が痛くて辛いのよ。」と一度っきりで、あの椅子に座るのは、懲り懲りだと思っていた。
母がそれほど行きたいのならと、結局映画会にお供をする事になった。行ってみると、以前にはなかった座布団が敷いてある。苦情が出たのだろう。スクリーンは四角くて、映画館ほど大きな画面ではない。私がトイレに行っている間に、母は席を移動して、前の方に座っていた。
 イタリアンプレート、スープ、プレート、デザートとコーヒー
イタリアンプレート、スープ、プレート、デザートとコーヒー映画が始まると、劇場のように、手を叩き、「わーハンサム、クーパーは、ハンサムだわ。」と声を出して感嘆している。静かにという合図をして手で口を押さえると、周りに人がいるのに気が付いたようで、それ以来、沈黙して画面に見入っていた。お芝居だと、声が思うように聞こえないのか、必ず居眠りしているのに、きちんと座ったまま、腰も動かさないで、映画の画面に吸い込まれているようだった。
私の方は、尾てい骨が痛くなってきて、向きを変えたりしながら見ていたのに、途中で居眠りしそうになった。前日夜中まで起きていたからだ。
 ワシントンホテルのレストラン
ワシントンホテルのレストランヘミングウェイの小説を映画化した、あまりにも有名な名作、もうすでに何度も見ている。映画でも何度か、ビデオも買って持っている。なのに、段々とその中に引き込まれて、佳境に入っていく場面になると、涙ながらに、感極まって。最後の場面は、いつみても、また新たな感動に胸を打たれる。
最近、涙を流さなくなっている母は、久しぶりに心を揺さぶられ、泣きながら、「ああ、本当に素晴らしかったえわね。」「クーパーは魅力的だわね。」何度も、その言葉を繰り返していた。
「映画が良いわ。大きな画面で見ると迫力が違うわね。また、どこかでするかしら。また見たいわ。」
「お尻が痛くなかった?」
「座布団引いてあったもの。全然痛くないわ。」
私は痛くて、と言うと、「貴方の方が私よりもずっと若いのに、身体が悪いから可愛そう。」なんて、気遣ってくれる。
この日の母は、随分元気で、頭も冴えている。母は共演のイングリッド、バーグマンのことは言わなかった。
「クーパーが素敵だ、素晴らしいわ。クーパーがハンサムだ、良かったわね。」
「誰がために鐘は鳴る」は父が好きな映画でもあった。父は、イングリッド、バーグマンが素晴らしいと絶賛していた。彼女の作品の中で、一番魅力的な映画だと。父はゲーリークーパーも好きだったけれど、ジョンウェインのフアンだった。恋しながら女性に触れることもなく、去っていく男の中の男役が得意のジョンウェインと、マカロニうウェスタン時代から、父が亡くなるまでずっと、クリント、イーストウッドのフアンだった。
ゲーリークーパーもイングリッドバーグマンも、この世の人ではない。共演者の殆どが他界しているだろう。永遠のスター、と言われるのは、こういうスターの若き姿に銀幕の世界で会えるからだろう。母にとって、ゲーリー、クーパーはまだ現存している人なのだ。
2008年06月23日
ふるあめりかに袖はぬらさじ

有吉佐和子の原作で、初演は昭和47年名古屋中日劇場での文学座公演で、杉村春子が主演の芸者、お園を演じた。 昭和63年に、杉村の当たり役であった、お園を板東玉三郎が受け継ぎ、以来繰り返し、公演されてきた。その名作舞台を、平成19年の12月歌舞伎座公演で、歌舞伎として発上演された「ふるあめりかに袖はぬらさじ」をシネマ歌舞伎として、7月4日まで、上映している。
舞台のような臨場感はないが、大写しの画面で、役者の細やかな表情まで映し出されるので、映画感覚で見るようにカメラの捉え方に工夫が見られる。舞台中継なので、臨場感を出すべく、拍手や客席からの笑い声が録音されているのは余計な気がする。拍手はまだしも、笑い声は、耳障りで逆効果になっている。
手頃な値段で、歌舞伎の名舞台が見られる機会があることは、歌舞伎フアンだけではなく、歌舞伎の楽しさを紹介し、歌舞伎フアンを増やす宣伝効果もあるだろう。
主演の芸者お園を演ずる板東玉三郎の見事な演技は言うまでもないことだが、歌舞伎とは違った、せりふまわしが、ふとテレビの対談などで聞く玉三郎の語り口に、声も話し方も似ていて、新派の舞台のような感じがする。
吉原から知っていた、花魁「亀遊」に七之助、唐人の通訳として雇われている、医学を志す青年「籐吉」に中村獅童、横浜の遊郭「岩亀廊」の主人に勘三郎の3人が、主要な役所を演じている。悲劇的な内容なのに、喜劇の要素がたっぷりで、笑いの壺を刺激する場面が多々あり、ユーモアたっぷり。他にも豪華な顔合わせで、海老蔵、福助、三津五郎 、橋之助、勘太郎、猿の助のスーパー歌舞伎のスターが勢揃いしている。
幕末、海港まもない横浜の遊郭「岩亀廊」で、若く美しい遊女が、カミソリで自害する。 その75日後に、自害した遊女の美談の作り事が瓦版として出回る。そこからこの遊郭の事情が変わって、話は流されて拡大されていく。
途中、10分間の休憩を挟んで、2時間55分の上映時間、11時半、3時、6時半の3回の上映で、大阪の松竹ピカデリー劇場で。
2008年06月10日
築地魚河岸3代目

http.www.uogashi.3.jp/movie/
築地と聞いちゃあ、見ないわけにはいけねえ。東京に行くと、私は必ず、築地に足を運ぶので、あの辺りはよく知ってる。目当ては、鮨くいねえ。
梅田の茶屋町にある「すし清」だって、築地で働く人からの口コミで、築地の店を知ってからのこと、築地にある2軒の店は毎夜、毎夜、満席で待たないと入れないくらいだった。場外市場にある、赤飯の鮨も美味しかった。築地の鮨屋は何軒か、違った店に入っているが、立ち食いの「まぐろ丼」も、2,3度食べた。他の店ではあれほど沢山のマグロは乗っていない。マグロと飯の分量がひっくりかえっているくらいだ。
映画の中で、よく知っている風景が映ると、故郷のような懐かしさを感じる。銀座から、聖路加病院の横を通って、築地まで歩き、鮨を食べて、晴海大橋の方にまた歩く。
今は、立て替えて、他のホテル名になってしまったが、イギリス大使館のすぐそば、半蔵門地下鉄駅を下りて、そのまま濡れずにいけるホテル「ダイヤモンドホテル」に泊まった。お堀端を通って、国会議事堂を見ながら、有楽町を経て、銀座まで歩く。「木村屋」で桜あんぱんを買って、映画を見るのもよし、日本橋にある「ブリジストン美術館」で休むのも良い。更に足は築地に向く。築地の本願寺で、有名人のお葬式に遭遇したこともある。
歩き回っていたので、あのあたりの事は手に取るようにわかる。歌舞伎座の、と映画の中で言えば、あああそこ、という感じに。


「築地魚河岸3代目」はコミックからの映画化らしい。築地に生きる人々の人情味溢れる物語で、霞ヶ関や六本木の住人とは、全く異人種かと思えるほどの、昔気質の江戸ッコ気質、やっちゃ場育ちの人達の生活ぶりは、かえって、新しい新鮮さを観る人に与えてくれる。築地の移転が取りざたされているけれど、新しく予定されている土地の汚染がひどいとか、築地は築地、今のままで、存続してほしいものだ。
ちなみに、築地魚河岸3代目は、シリーズものとして、フーテンの寅さん、釣りばか、の3代目として松竹が育てるつもり。来年の2作目が決定している。
2008年06月09日
償い

リーガロイヤルホテルの画廊で友人が個展をするのだけど、大阪は不慣れなので、と言う友人と紀ノ国屋の前で待ち合わせて、朝一にしか上映していない「償い」を一緒に見てもらった。先日、満席の立ち見で諦めた作品だ。パリからの帰り、飛行機の中で見たことはみたけれど、途中で居眠りしていた部分があったので、もう一度、きっちりと見たかった。映画館の大画面で見ると、全く違った作品のように感じる。
衣装の細部、景色の色、人物の表情など、小さなビデオではとても味わえない豊かさで迫って来る。内容はわかっていても、全く違った映画を見たという印象が深い。
この小説の映画化は無理だと言われたらしいが、時間と空間が、複雑に交錯していて、 イマジネーションの時間と、現実に起こる時間を、二重に映像で表現するという方法が何度か使われ、それが観客のイマジネーションを更に要求する。
勿論、この小説は作家によって作られたフィクションなのだが、その中の現実では償えなかった、悲惨な現実を、作家のイマジネーションによって、「幸福なハッピーエンド」に書き換える。実際には、この小説家が13才に嘘をついた事によって、一人の有望な青年の人生をどん底に陥れ、戦場で悲惨な死を遂げさせ、彼を愛した姉も、戦下の犠牲者として死なせる結果になる。
「戻ってきて。もう一度、やりなおす事が出来るわ。」と彼を励ます恋人からの手紙を胸に抱き、「岬の家に行きましょう。ここで待っています。」という写真を見ながら、恋人との幸せな場所に帰る事だけを夢見て、戦場で息絶えた恋人。同じように傷ついた戦士達の世話をしながら、彼の消息と帰りを待ち続け、地下鉄の崩壊で水死した姉。
 リーガロイヤル、日比谷花壇
リーガロイヤル、日比谷花壇私は、この小説に中で、作家が表現したかったのは、どのような悲惨な現実、退屈な人生、ドラマティックではない平凡な日常、戦時下にあっても、監獄の中に閉じこめられていても、人間は自由を得ることが出来るし、幸福になれるということなのだと思う。
戦場で死んでいく恋人が、見続けていたのは、彼女とやり直せる未来、彼女を胸に抱くこと。姉の頭の中にあったのは、恋人への想い。共に生きる幸せ。取り返しの付かない罪を犯し、償いをしたいと看護婦になった妹は、作家への道を歩む。想像の世界の中で、彼女は現実から逃避することが出来た。「書いている時、ある種の幸せに浸っている」というマルグリット、デュラスの言葉が。「人は監獄に幽閉されている時、最も自由になれる」と言った、サルトルの言葉が。

映画の中で、戦場で、食べ物を口にしながら笑っている戦士達のドキュメンタリー映像が挟まれている。彼らの幸福な、くったくのない笑顔。彼らは、現実の中にあって、想像の中で笑っている。
2008年06月07日
母を通して思う


あいも変わらず、有馬温泉に母のお供ででかけた。4日ほどまえに、「太閤の湯」に母を連れていったばかりだったので、母は、プリンセス有馬につくと、ホテルの窓から、「太閤の湯」の建物を眺めて、「良かったわね。」覚えている様子。ホテルは、有馬温泉の町を見下ろす高台にある。温泉街まで散歩するには、急な坂道なので、母の膝では無理。
森林浴をかねて、近くを散歩するだけだでも、小一時間くらいかかる。去年の12月から導入された、赤湯は、一段と色が深く、沈殿物が身体にまとわりつくくらいに濃くなっていた。心臓は、母の方がいたって丈夫で、長時間湯船に浸かっていても平気の様子。


お風呂に暖まり過ぎたのだろうか、食時が終わる頃に、母は突然気管支が詰まったと言って、咳き込んだ。大した事はなかったけれど、初めての事なので、おろおろしてしまった。今夜はワインも殆ど口にしなかった。好物のお肉が美味しくなかったようで、一口食べただけだった。
最近、気管支が変なのだと、母は言う。もう長くないかもしれないと弱気な事を言われると辛い。百才まで生きるような気がすると言われると、ほっとする。


人間はおしなべて皆、死ななくてはならないのだから、と自分に言い聞かせるものの、いつまでも生きていてほしいと願う。死ぬのはいやだわ、と言われると身体が痛み、心が冷える。湯船の中で、「上手に歌いたいのに、思うように歌えない。この歌が好きなのよ。」と機嫌良く歌う歌は「アカシアの雨に打たれて、このまま、死んでしまいたい。」
最後は「冷たくなった私をみつめてあの人は、涙を流してくれるでしょうか。」


つきあって、うなずいて聴いている私は、よけいに落ち込んでしまう。母を通して、自分の死を考えてしまう。願わくば、旅の果てに、人知れず仏陀のように、とかっこつけて友人に言ったら、「本当はメチャクチャわめいて大変だったんですって。」と友人が教えてくれた。若い頃は、雪山をどこまでも歩いて気を失いまで、とか、湖水の底に眠りたいとかロマンチックな死を想像していたが、死は遠くにあって、無縁だった。今も無縁かもしれない。死に直面する病にかかった人は違う。人生観がすっかり変わったと誰もが言う。 人は、死に直面して、初めて本当の生き方を考えるのかもしれない。本当に生き始めるのかもしれない。
母も私も、死の漠然とした恐怖を見つめているようだが、死の疑似体験をした人は、生きることをみつめている。生きることしか考えていないだろう。

2008年06月07日
譜めくりの女

日曜日、朝一番に、梅田のテアトルに行くと、映画の日なので、おめあての「つぐない」は既に立ち見席しかなかった。どうしようかと迷っていると、ぞくぞく後からやってくる女性達は皆、逞しくも立ち見承知でチケットを購入している。
私は、無料の株主チケットなので、また改めて来ることにして、もう一つの映画「譜面をめくる女」の方に予約を入れた。というのも、レナウンの株主招待券をもらっていたので、そちらの方を先に行ってから、ついでに映画も1本見て帰りたかったから。
地下鉄のコスモス駅で乗り換えて、モノレールで2つめの駅で降り、歩いて5,6分と書いているけど、実際には10分かかって、「レナウン花と実の会場」に着いた。
会場は空いていて、昔のような活気はまったくない。以前は、両手一杯に買い物をした客に出会ったけれど、最近では、洋服よりもむしろ、その会場出口に店を構えている、食料品や、医薬品、実用品などの店で、どっさり買い物をして帰る人が目立つ。
私は2時間、会場の中で、最も値打ちのある安そうなものばかり探して、コート2枚とセーター、カーディガンを買った。映画の予約をしてあったことを悔やみながら、大急ぎで会場を出た。会場の外に出ると、休憩のコーナーがあり、柿の葉鮨や、薩摩揚げ、パンなどが美味しそうに匂って来る。パウンドケーキは3つで1000円、油や乳製品、しいたけ、ノリ、などの乾物、小倉屋の昆布、コーヒー、紅茶に、化粧品に、健康食品など、どれもすごく安い。
物価がどんどん上がっているので、買い込んでおこうという人達で、このあたりは混雑していた。空きっ腹をかかえて、通り抜け、走って地下鉄の駅へ。

梅田に着くと、まだ時間があった。紀ノ国屋の前のイベント会場で、「ガムの日」というイベントが行われていいる。おじいさんの話が終わったところで、これから無料でガムが配られる。そのおじいさんは、有名人らしく、どこかで見た記憶がある。一緒に写真をと申し出る人達と写真に収まった所を1枚取らせてもらった。
ガムをもらうのに待っている時間はない。近くの、マクドでフィレオフィッシュを買い、水を買って、入館した。照明が消える所で、予行編を見ながら、手早く、音を立てないように気にしながらハンバーグを飲み込み、水を放り込む。
 このおじいさん、見たことあるなあ
このおじいさん、見たことあるなあフランス映画は、人間の心理を描いたものが多いが、これもその典型。神経質で潔癖性の完全主義の女の子は、音楽学校の受験を目指して猛練習する。落ちればピアノをやめる覚悟で。少女の出だしは順調で、素晴らしい演奏振りを発揮している。受験会場に入ってきた女性が,試験官の女性ピアニストにサインを求めると、彼女は演奏中にサインをする。自分の演奏を無視された少女は、全く調子が狂ってしまって、惨めな結果に終わる。
大人になり、実習にやってきた弁護士事務所は、かつて自分を無視したピアニストのご主人の仕事場で、臨時の仕事で自宅に入る。交通事故の後遺症で、ピアノに自信がなくなっているピアニストに、譜面をめくる仕事を頼まれる。かつての少女は、ピアニストが持てる全て、ピアニストとしての生命、才能ある息子のピアニストへの道、夫との愛の生活、裕福な生活、全てを奪い、復讐を遂げる。静かに、優しく、怖ろしいほどの冷静さと残酷さエレガントさで、人間に潜む、欲望と嫉妬を見事にあやつって。いかにもフランス映画らしい映画だ。